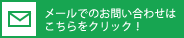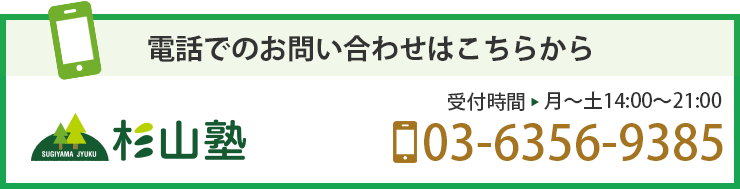あの日常が再び ver2
(前回からの続き)
工学部を志望していたため、まず数学と物理を中心に進めていきました。
私が受験日までのスケジュールの原案を立て、理系の講師と彼との3人で話し合いながら進めていったんです。
前回のブログでも述べた通り、いずれの科目も基礎的な理解にまだ不安な部分があり、これまでの復習をメインにせざるを得ない状況です。
残り時間を考えれば、復習を中心に据える余裕はないかとも思えるのですが、基礎が揺らいでいる状況でビルを建てても倒壊することは目に見えています。
ここは腹を括って、基礎が固まるまで新しいことには手は出さずに進めることを彼ともよく話し合いあました。
ここで大切なのは、受験するの本人がいかに納得して基礎固めをできるかです。
当然周囲の同級生は先へ先へと進めており、その様子を見聞きするにつれ不安を漏らしていました。
その度に、同級生とはスタートの時期が違うことや現状の課題を解決しないと的確な対策も打てないことを説明して、不安を抑えることに日々注力していました。
7月から10月の時期は模試の成績も伸びず、彼の不安は計り知れなかったと思います。
ただ、模試でできなかった単元も基礎固めのチャンスと考えて割り切れば良い、というようなアドバイスを繰り返して復習に注力をしてもらう日々でした。
そうして11月に入り共通テスト対策に本腰を入れ始めた頃から、基礎が固まってきた印象を受けました。
理系の講師との会話でも、以前は答えられなかった質問に答えられるようになり、さらに一歩突っ込んだ質問もできるようになっていたんです。
そうなると問題を解くスピードも加速度的に速くなり、間違える箇所も絞り込まれ、短時間の復習で済むような状況になってきました。
ここからは、持ち前の集中力と持続力で次から次へと課題をこなしていきます。
高校受験の時もそうでしたが、勢いに乗った時の彼は止められないという感じで、こちらはペースを崩さないように見守っているという状況です。
12月に入ってからは毎日のように塾に来て、自宅と塾の勉強時間をしっかりと決めて休むことなく勉強を繰り返していきました。
そして共通テストを迎えたのですが、日々の努力が形に現れこれまでで一番良い成績を取ります。
そうして併願の私立大学の合格を勝ち取り、最終的に第一志望校の国立大学に合格したわけです。
結果に結びついたことが素晴らしいのはもちろんですが、それまでの妥協しない努力の過程が特筆ものでした。
目標を決めたらそこに向かってひたすら努力を続ける。
この姿勢が結果に結びついたのであり、遡れば高校受検での成功体験が自信となり努力もパワーアップした印象を受けます。
もちろん合格してくれたことが大変嬉しいのですが、彼の6年間の成長過程をつぶさに見せてもらえたことが何よりも大きなご褒美でした。