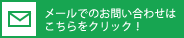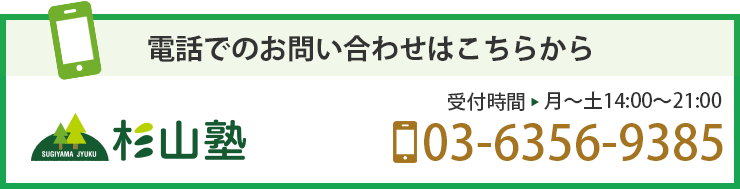「教えない」ことの意味
最近「教えない塾」という形態の塾を見かけることが増えてきました。
「教えない」というと、「それじゃ塾じゃないじゃない」と言われそうですが、決してそうではないと思うんですね。
例えば、まずは例題を基に生徒に問題を解いてもらう、そのうえで分からないところは解説する。
大雑把に言うと、生徒の自主性を促しつつ自分では解消できないところを指導していくというスタイルだと思います。
最終的に勉強は自主的に行わないと理解は進みませんし、知識の定着もおぼつかないというのが現実でしょう。
学習塾の指導スタイルの流れも、集団塾全盛の時代から個別指導へと移り、その個別指導が手をかけすぎて生徒の自主性を育てらないという側面を踏まえて、「教えない塾」というスタイルが生まれたのかもしれません。
私は個別指導でも自主性を養うことは十分可能だと思っています。
ただ、手取り足取り指導する個別スタイルではなく、考え、手を動かす時間と距離間が必要です。
時間は生徒の現状によって5分なのか10分なのかは異なります。
また、距離感はあえて隣には座らない。すぐ手の届くところに助けてくれる存在がいるような甘えを生みださなという意味です。
個別指導である以上、個別に指導方法も変えていく。指導する側としては大変な労力です。
でも、生徒の甘えを許さない以上、自分も甘えていられませんからね。